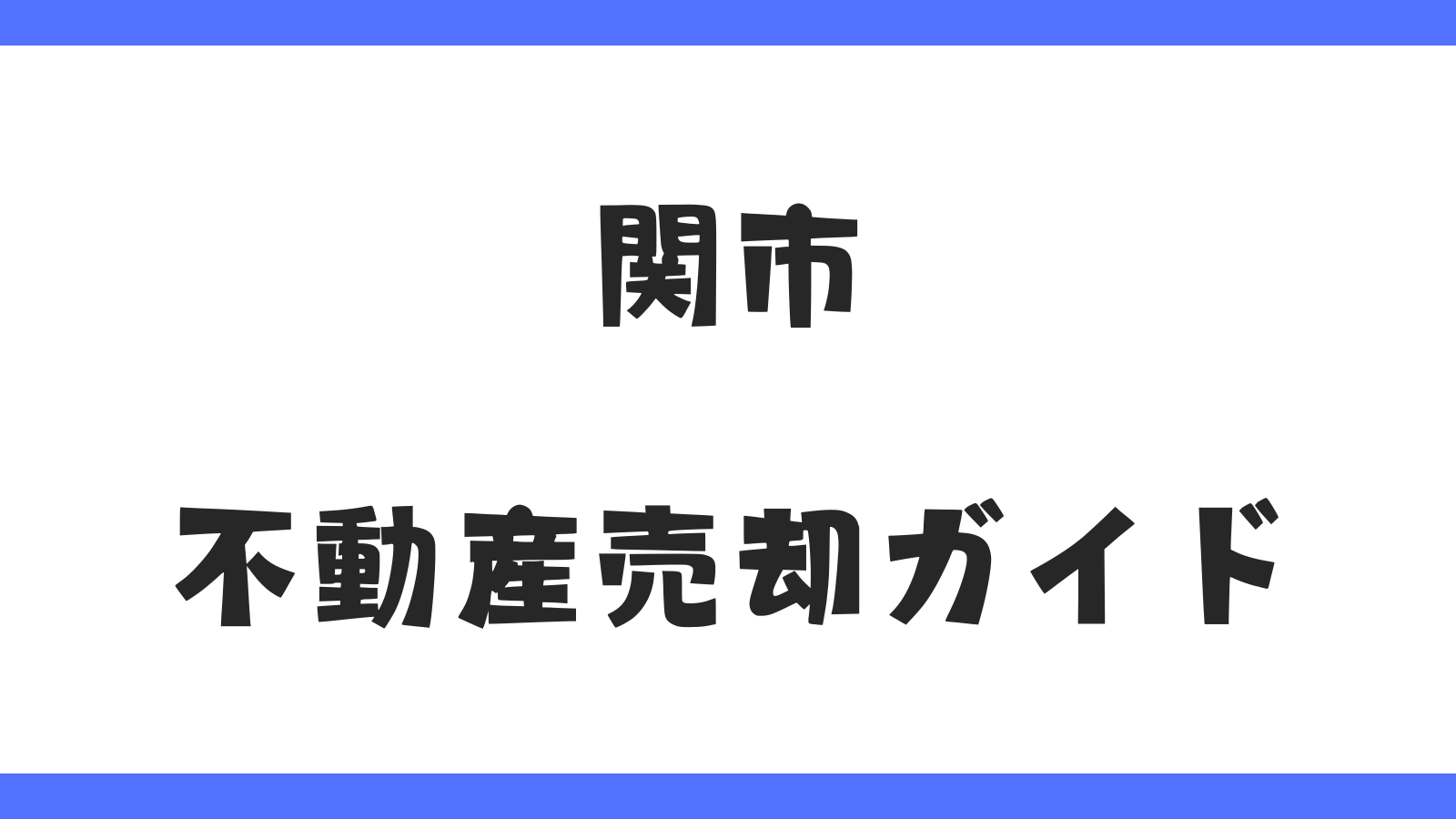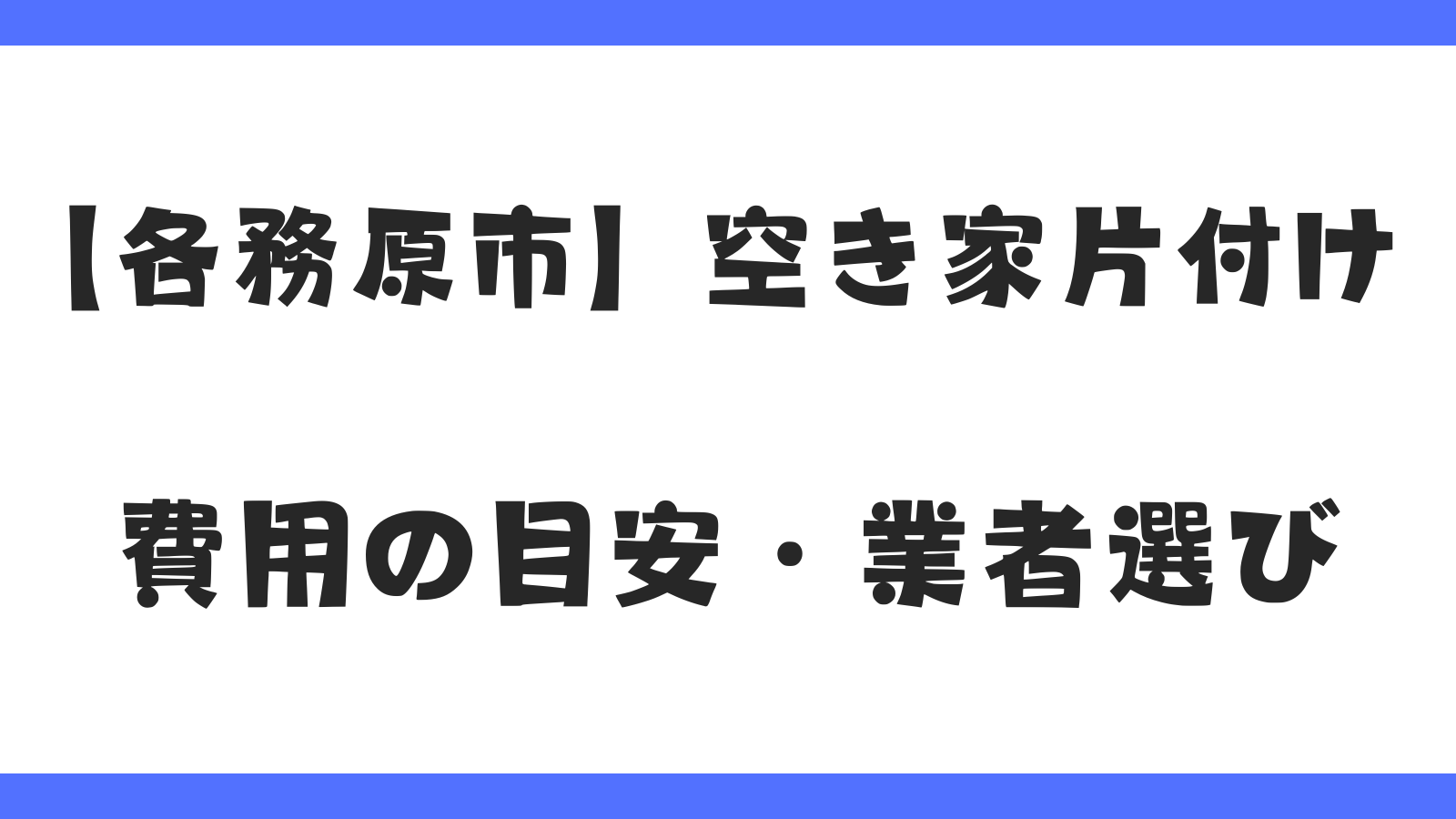不動産の個人売買はできる?トラブルや注意点を解説|結論:オススメしません!
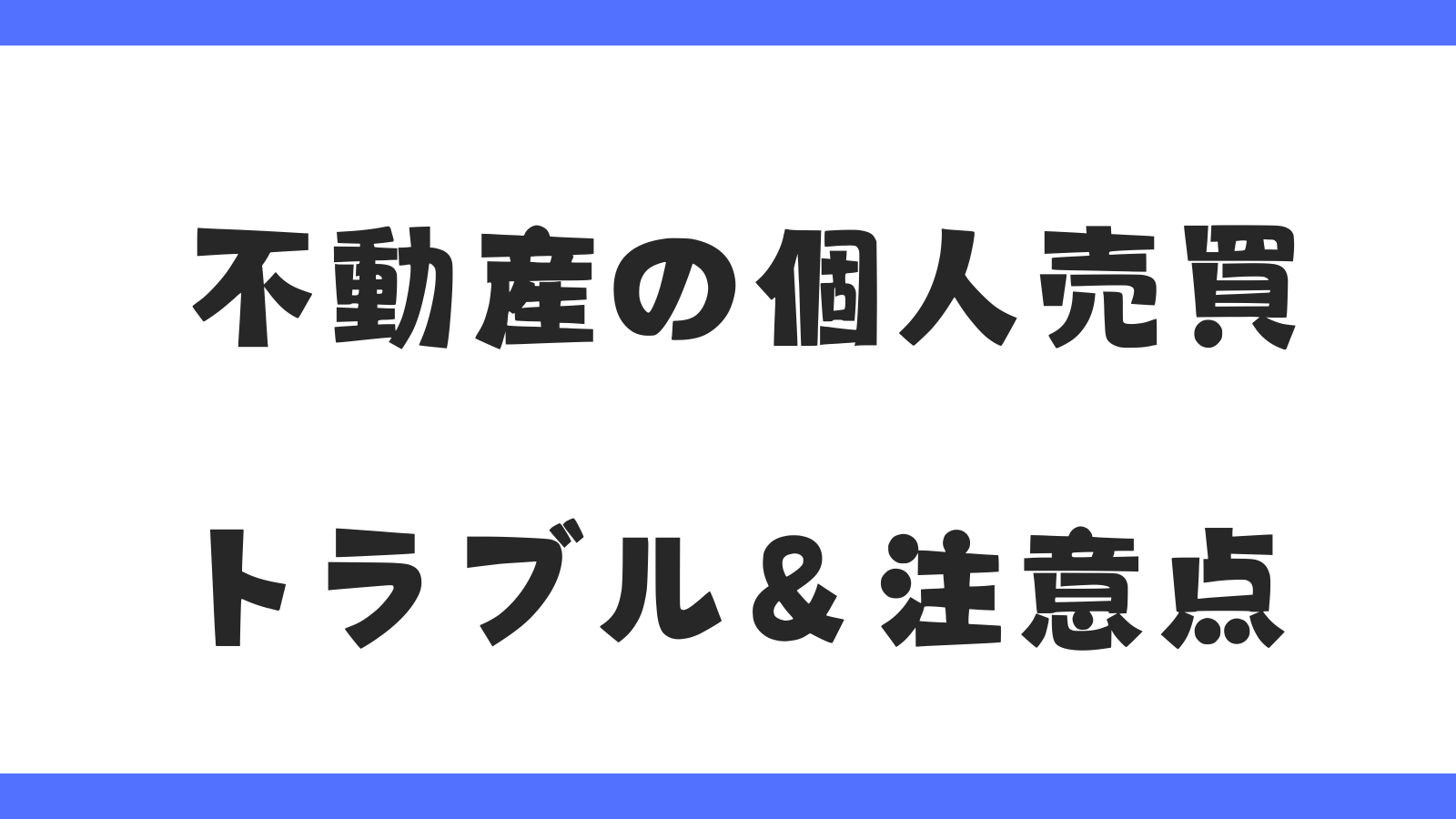
家の売却もしくは購入を考えている人のなかには、不動産会社を通さずに直接、個人間で売買を検討している人もいらっしゃると思います。
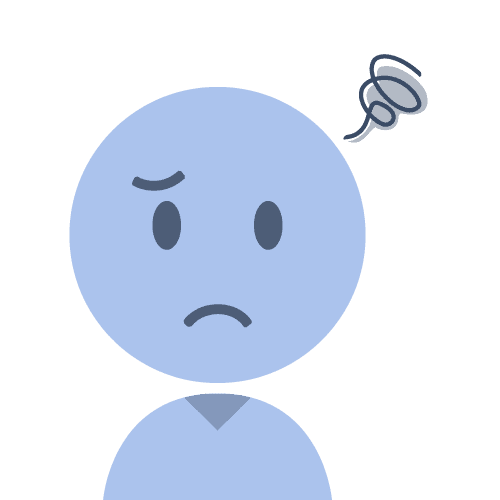
- 欲しい物件が見つかった
- 家を買いたい人が見つかった
- 売主(買主)と話して売買価格が決まった
- 仲介手数料を払うのもったいないし直接売買したい
でも、不動産の個人売買ってできるの?よくあるトラブルは?注意点は?
本記事では、不動産の個人売買について詳しく解説しますので、このようなことでお悩みの方は最後までご覧ください。
不動産の個人売買は、法的にはできる
不動産の個人間売買は法的には問題ありません。
でも売主・買主が一般消費者(不動産の素人)である場合、揉める可能性が高いのでオススメできません!
不動産の個人売買のメリット
不動産の個人売買の一番のメリットは、不動産屋に支払う仲介手数料がかからないことです。
また、売主と買主の間に不動産屋が入らないことで、売主・買主のペースで商談を進めることができます。
不動産の個人売買のデメリット
不動産の個人売買の一番のデメリットは、契約上のトラブルを起こす可能性があることです。
契約書の雛形はインターネット上でダウンロードできますが、詳しい取り決め事を文字に残さなければ後でトラブルになります。でも何を記載すれば良いのか、不動産売買の素人ではわからないと思います。
個人売買でよくあるトラブルと注意点
適正価格がわからない
不動産業界にいない人にとって、不動産の査定は非常に難しく適正価格を算出することはできません。
個人売買のほとんどのケースが、客観的な価格ではなく、”売主がいくらで売りたいか、買主がいくらで買いたいか”というお互いの主観で決まることが多いようです。

不動産屋に査定依頼するのが一番早いのですが、それが難しい場合はこちらの方法をお試しください。
土地の固定資産税評価額÷0.7の計算式で、大体土地の適正価格が算出できます。
契約内容のトラブル
不動産屋が仲介に入ればトラブルになりそうな点については契約書に明記されますし、重要事項説明書を作成してもらえますが、個人間では調査も自分たちで行います。
そのため、契約前に聞いていた内容と違う、言った言わないことによるトラブルが発生することがよくあります。
契約書の不備
不動産に関する専門的な知識を持たない個人が売買契約書を作成すると、適正な書類を作成できない可能性があります。
例えば、収入印紙の貼り忘れや割り印の押し忘れ、記載すべき内容の漏れ、誤字脱字など。
個人売買の契約書では住宅ローンが通らない
不動産を購入する場合、多くの人が住宅ローンを組みますが、不動産の個人売買では住宅ローンの融資審査が通りにくいので要注意です。
住宅ローンの審査を通すためには、個人売買で入手が難しい重要事項説明書の提出が求められるので、信頼できそうな不動産屋に作成してもらう必要があります。

仲介ではなく、書類(契約書や重要事項説明書)作成のみも対応しています。会社ホームページからお問い合せください。
不動産の個人売買の流れ
不動産の個人売買はオススメしませんが、どうしても個人売買をしたい人は商談の流れを理解してください。
個人売買の流れ|家を買いたい人の目線
直接物件を探すパターンと共通の知り合いを通じて紹介されるパターンがあるかと思います。
直接、所有者と会って正直に売ってもらえるか確認します。
所有者が売却の意思があることが確認できたら、価格交渉をし、物件価格を決めます。
契約書を作成し、お互いに署名捺印をします。
収入印紙を貼ることを忘れずに。
残金の支払いが終わり次第、所有権の移転の手続きをします。
通常、司法書士に所有権移転登記の手続きを依頼します。
個人売買でトラブルを防ぐためのチェック項目
抵当権が設定されているかどうか
抵当権が設定されている場合は、抵当権抹消登記をしなければ売買できません。
その場合、抵当権が設定されている債権者(金融機関)に相談して、抵当権抹消手続きを行います。
売主情報は最新になっているか
所有者が既に亡くなっている先祖だったり、所有者の住所が実際の住所と違ったりする場合、所有者の情報を最新のものに変更してからではないと売買できません。
所有者が自分で変更登記することもできますが、難しければ司法書士に依頼します。
買主にとっての購入する目的が達成できるか
不動産を購入する目的はそれぞれですが、そもそも購入する目的を達成することができるかどうかを確認する必要があります。
例えば、「市街化調整区域や接道要件が満たさないため家が建てられない」、「事業用として購入しても用途地域や条例などの制限によって事業ができない」などが挙げられます。
必ず役所の都市計画や建築指導の部署に確認をしましょう!
境界の明示をするかどうか
境界のトラブルはよくあることですが、売買後に揉めないようにできれば確定測量することをオススメします。
ただ実際に売主が業者でない場合は、測量の費用と測量にかかる日数の問題で、確定測量までは行わないケースが多いです。
確定測量を行わない場合は、境界の明示はしない旨を明記する必要がありあす。
契約不適合責任の取り決め
契約不適合責任とは、売買や請負などの契約で引き渡された目的物が契約内容と合っていない場合(雨漏り、シロアリ、設備故障など)に、売主が買主に対して負う責任のこと。
売主と買主が一般消費者の場合、売主の契約不適合責任の期間は3~6ヶ月にする場合が多いのですが、免責、つまり一切責任を負わないという契約にすることもあります。
中古物件の場合は、よく揉めるポイントなので、契約書に必ず明記しましょう!
地中埋設物の処分費の負担は?
家を建て直したり駐車場を整備したりする場合、解体しますが、解体した際に土の中から瓦や基礎、コンクリートガラなどが出てくることはよくあります。
そのケースを想定して、地中埋設物が出てきた場合の処分費を売主・買主どっちが負担するのか、また有効期限をいつとするのか、契約書に明記する必要があります。
所有権移転登記は司法書士に依頼する?
個人売買を検討する人は、所有権移転登記も自分でやろうと考える人が多いような気がします。
所有権移転登記も自分でできますが、できれば司法書士に依頼することをオススメします。
どうしても自分で登記手続きをしたい場合は、事前に法務局の無料相談に予約して手続き方法について理解してから、決済・引渡し当日に臨みましょう。

仲介ではなく、書類(契約書や重要事項説明書)作成のみも対応しています。
引渡し後、トラブルにならないようにヒアリングしながら必要書類を作成させていただきます。
まとめ
不動産の個人売買について詳しく解説しました。
繰り返しになりますが、様々なトラブルが想定されるため、不動産会社に仲介してもらうことをオススメします!
今回は以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。